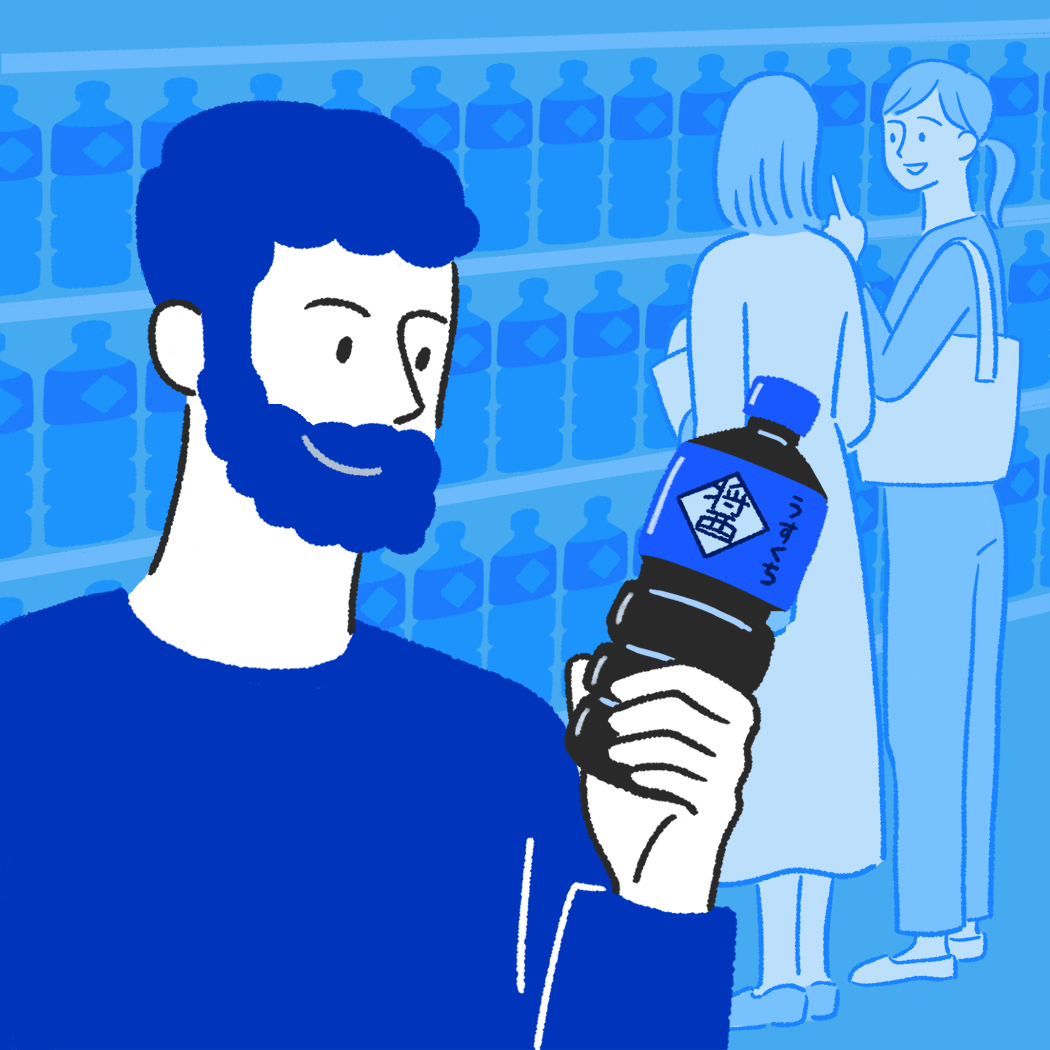変化のはじまり「地域の個性」の持続への貢献を問われる小売チェーン
過疎地では生活必需品の提供場所として、大型小売チェーン店の誘致が進められる。しかし、地域の商店街が利用客を奪われることや、街の景観に個性がなくなることなどのリスクに備えて、出店する大型チェーン店側には地域貢献のガイドライン整備が進んでいる。地域住民は暮らしの利便性の観点から大型店の出店を歓迎しつつも、同時に商店街や地元産業が衰退してしまう危機感に葛藤している。
可視化で進む地域経済の好循環

-
現在の価値観便利で安価な大量生産品の流通がうれしい
将来の価値観不便で少量生産でも、地域の物の流通がうれしい
全国各地でチェーン展開をしている小売店は、地域貢献の義務を果たすため、店舗と地域のハブになるコミュニティマネージャーを配置する。彼らは地元産商品の積極的な取り扱いや、地元企業との共同開発などで、地域の魅力を広める役割も担う。また、自社のポイントプログラムを地域内の各商店でも使えるように連携し、地域の経済振興を促す。
コミュニティマネージャーは商工会議所や産業団体と連携して、消費者や事業者も参加できるリビングラボを立ち上げる。例えば小売店が発行したポイントを、地域活動への寄付に回したり、子どもたちにお小遣いとして渡すことで地元商店での買い物習慣をつくったりするなどの施策を生み出し、地域活性化をめざす。また、その地域で使われているポイントの流通データは、大型出店企業がどれくらい地域に貢献しているかを、生活者が確認するためのものになっていく。
ブロックチェーン技術のさらなる普及で、チェーン店が扱う商品の背景にあるデータの可視化が進み、その流通が地域に与える影響が詳らかとなり,海外のサプライチェーンを経たものなどは,地域経済に悪影響だとして規制対象になる。また商品開発についても、地元特産品や地元工場の使用を一定比率以上とするガイドラインが制定され、地域に根差した開発が主流になる。
生活者は流通データを見ることで,地域経済に良い影響をもたらすチェーン店の取り組みを見つけその存在を歓迎し、自らも家計の一定の割合が地域貢献につながるよう、消費スタイルをコントロールする。また、企業都合の決断が地域経済のバランスを崩さないように、消費者同士が連携する。例えば売り上げが悪い食品の学校給食での活用を検討するなど、地元産の商品開発や存続に生活者が積極的に関わるようになる。
地場文化を象徴する情景の創造

-
現在の価値観地域の情景は、いつも当たり前に存在しているもの
将来の価値観地域の情景は、みんなでお金を出し合い作っていくもの
地域のお店の閉店は、たとえ小さくとも近所の人の動線を変えて、地域がひとつの個性的な情景を失うものだと考えるようになる。これを防ぐため、まちづくりに関わる企業は、宿泊施設などさまざまな機能を追加して、お店を長く続けられるように計画する。特徴的な自然や文化財を持つ地域では、大手の旅行事業者などが一帯をリノベーションして収益化を図ることで、自然・建物・人の往来から成る情景を存続させていく。
このような事業側の努力もあり、見た限りでは何を専門に扱っているのか判断しづらいお店が各地域に溢れる。人々はそのような混沌や違和感を含んだ情景から、その土地の個性を再発見するようになる。さらに、そうした地域での買い物は、単に日用品を購買するための行為ではなく、地域産業への支援や、地域そのものへの愛着を示す意味を帯びていく。
過疎地域では、法人・個人を問わず、後継者不足からやむを得ず不動産を手放すケースが増える。自治体は、地域の象徴が意図せず失われることに備えてガイドラインを設け、不動産引き継ぎに関わるサポートや、市民が合意形成に参加できる仕組みを作る。
土地や建物と住民の動線が生み出した情景は、共有財産として引き継ぐべきだという認識が広がる。そして、特定の所有者や事業主の都合で重要な不動産が放置されたり、取り潰されたりすることがないよう、周りの住民たちによってその情景を維持するためのコミュニティファンドが作られていく。地域外の事業者が新たに参入を計画する場合は、地域で引き継がれた文脈に沿うことがファンドから求められる。