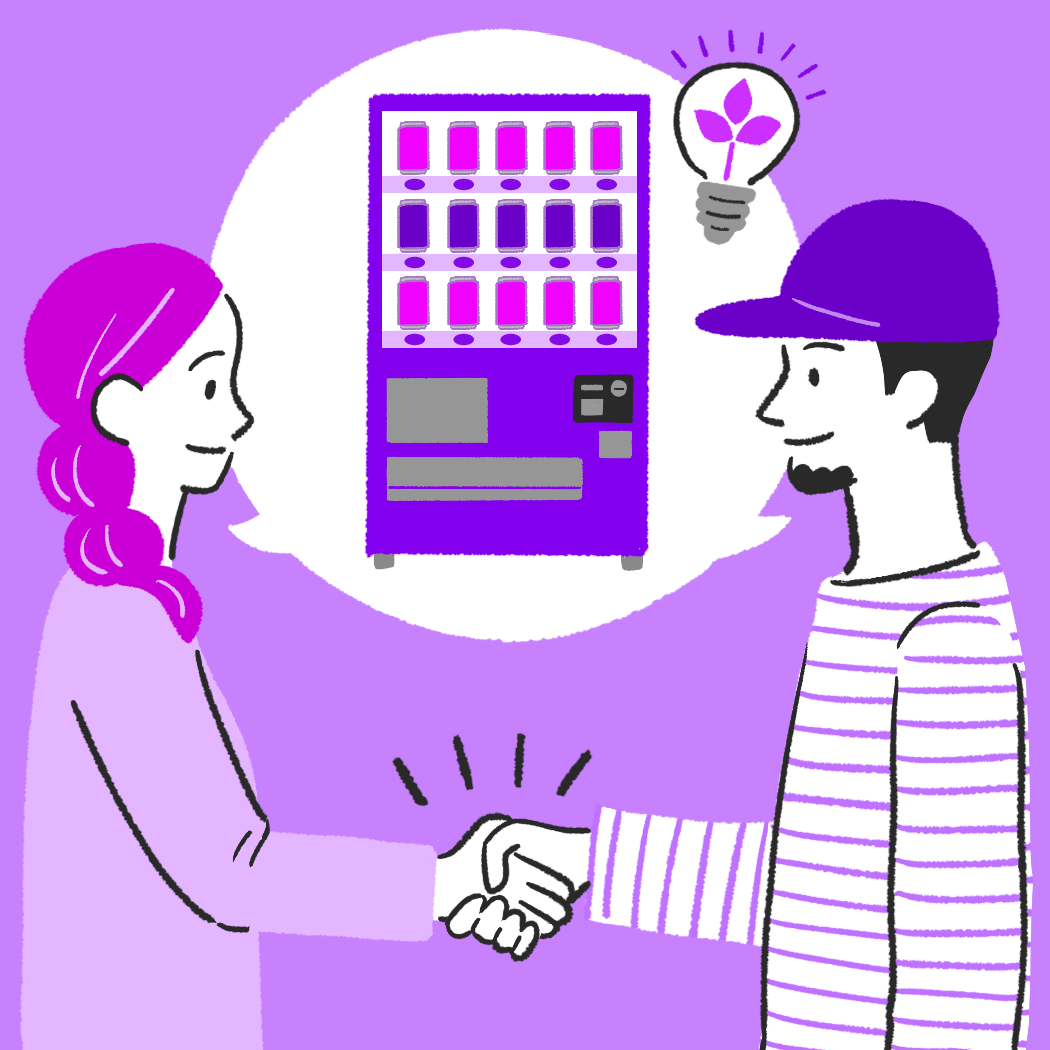変化のはじまりパイを奪い合うことで弱体化する地域や産業
資源の調達や顧客の奪い合いで、企業間の競争は激しさを増している。従来型の市場競争は、ある時点まで経済発展に貢献したが、さまざまなリソースが限られる時代では企業の衰退を招き始めた。人口減少時代に消費者という限られたパイを巡って企業間が争う中、目先の価値で商品やサービスを選ぶだけでは、地域社会が持続できないことが人々に突きつけられている。
地域経済を支える企業の協調関係

-
現在の価値観地域企業の商品・サービスを利用して地域を応援したい
将来の価値観地域リソースの有効活用のため地域内で協調する企業を応援したい
過疎化が進む地域では、リソース不足によって廃業する事業者が増える。産業の衰退によって地元が失われる危機意識から、行政の補助やUターン者をあてにしない、地域に残された人々主体の持続可能な地域づくりが活発になる。
地方の企業や組織は、「一丸となって地域を発展させる」という目標を掲げて、お互いに競争を避けながら事業を行う自律共生型コミュニティを築く。企業がお互いの役割を尊重しながら提供するコンテンツは、連携することで回遊性のある新しい消費体験を生む。観光客は個別のお店やスポットを目当てにするのではなく、その地域一帯でつながっているテーマを楽しみに、その場所へ訪れるようになる。
地域の発展には、企業や自治体などの組織間連携が必要不可欠になる。地域には事業者間の連携を取りまとめるコンシェルジュが登場し、地域事業者はAIを用いたビジネスマッチングによって、限られたリソースを活用していく。
貴重な地域資源の有効活用を望む住民は、複数の企業が協力して生み出した商品を優先して利用するようになる。また、都市部など地域外のチェーンは地元とのつながりが薄いと避けられる傾向に。そのような風潮を感じた地域外の企業は、コンシェルジュやAIの仲介を利用して、「地元の人々に人気の菓子に合うオリジナルコーヒー」を開発するなど、自社の商品と地元企業との接点を模索する。
ライバル企業をつなぐソーシャルグッド意識

-
現在の価値観ソーシャルグッドへ取り組む企業を応援したい
将来の価値観競合同士で協調し、ソーシャルグッドへ取り組む企業を応援したい
サステナブルレポートの義務化により、企業は環境問題や地域との関わりを考慮せざるを得なくなる。環境負荷の可視化するブロックチェーン技術が広がり、どの事業者がより誠実に地域と向き合っているかを明らかにする。
消費者はそのような情報の透明化によって、地域貢献度の高い商品を選択しやすくなる。ソーシャルグッドの意識が高い人々は、ビジネス都合による企業間の競争によって、環境負荷が高くなることに疑問を抱き始める。各社が同じような飲料を自販機で販売する様子が嫌われるなど、一社単独の企業活動に限界が生まれる。
サプライチェーン内の人権や環境リスクに対する適正評価が必須となる法規制が進む。従来のビジネスモデルや業界構造では適正化に限界が訪れ、自社のサプライチェーンを超えた変革が必要になる。これまで競合だった企業が、人権尊重、環境負荷の低減、地域発展を一緒にめざす、協力パートナーへと変わっていく。
生活者の意識も変わり、企業がおのおので社会貢献する個別最適な取り組みではなく、複数の会社で手を組む全体最適な態度を求めるようになる。例えば、他社の廃棄予定の在庫から新たな製品を生み出すような、サプライチェーンの連携が注目される。以前から見られるようなソーシャルグッドから生まれたつながりだけではなく、本業にも直結した互いの知見や技術を生かすことで、商品・サービスの品質向上につながる。