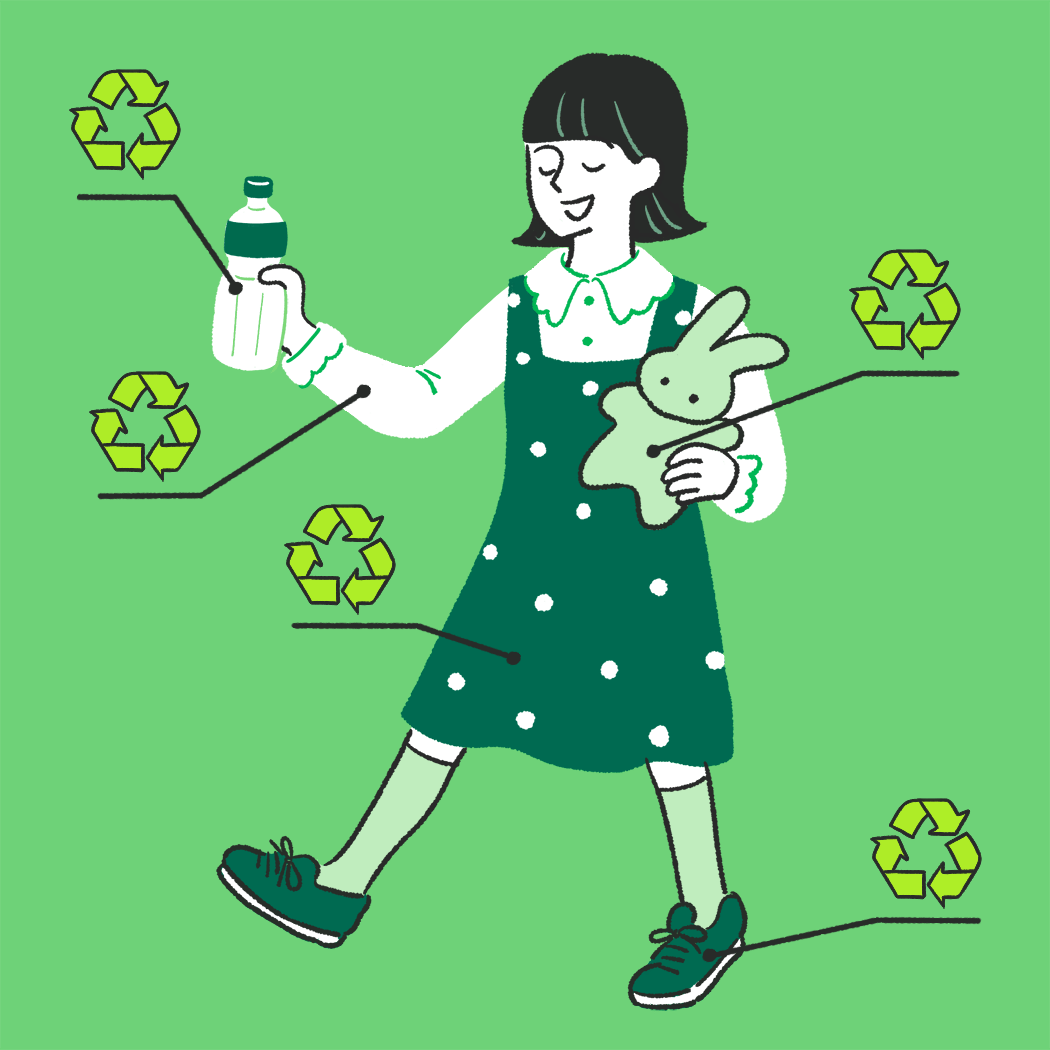変化のはじまり資源循環への関心の高まり
大量生産~大量廃棄の経済エコシステムは、資源の枯渇や環境汚染の観点から、サーキュラーエコノミーへ移行することが求められている。この流れを受けて、リサイクル品や再生材を用いた製品の流通が広がっているが、あらゆる不要品を可燃ごみとして扱う消費者の習慣や、企業にとって高効率な大量生産システムが、循環型社会への移行を困難にしている。
資源の循環力で測られる地域の暮らしやすさ

-
現在の価値観物を買いやすいことが街の魅力
将来の価値観物の手放しやすさが街の魅力
多くの地域でごみ焼却施設が老朽化し、修繕や建て替えをするか、もしくは他地域と連携してごみ処理プロセスを抜本的に変えてしまうかという選択肢に迫られる。特に人口減少エリアは、維持管理コストを確保できないため、焼却施設を持たずに、地域独自の資源循環システムや分別ルールを設定することを決めていく。
こうした流れが、モノの買い方やごみ捨ての習慣に関する生活者の意識を変えていく。環境意識が高い生活者は、コンポスト導入やリユース活動に積極的になり、行政のごみ処理の負担軽減に貢献する。一方で、細かい分別ルールに則る手間を省くことを目的に、廃棄しやすい素材の商品を消去法的に購入する人々も出てくる。
各地でごみ処理方法が多様になり、行政に代わって、地域の中小企業や環境活動グループが資源回収や再利用を担う例が多く登場する。高コストながらも低収益となってしまう彼らの活動を継続させていくため、資源循環の価値がさまざまな視点から数値化され、対外的な説明と資金集めに役立てられていく。
このように新しい技術で得られたデータは地域ごとに『物の買いやすさ・手放しやすさ』や『資源循環意識の高さ』などの指標に加工され、人々は地域間で移動する際に参照するようになる。資源循環の意識が高い人々は、これらの指標を自分の価値観やライフスタイルと照らし合わせることで居心地の良い地域を見つけ、居住地を選ぶようになっていく。
「消費者の返却」が一体化した企業のモノづくり

-
現在の価値観モノづくりの環境に対する責任は、企業自身が果たすもの
将来の価値観モノづくりの環境に対する責任は、
企業と生活者が一体で果たすもの
モノづくり企業にはLCA(Life Cycle Assessment)が義務化され、環境負荷のデータ開示が必須に。また、あらゆる企業活動が定量的に評価されるようになることで、これまで企業が環境に貢献するとして活動してきたことがグリーンウォッシュと見なされるケースが多発する。
消費者は自分が好きなメーカーの商品を手にするまでの流通過程で、多くの企業が関わることが環境負荷を高め、メーカーの評価を下げてしまうことを懸念するようになる。彼らはメーカーと直接取引の関係を築き、環境商品の直接購入や包装の返却を行いながら、企業の環境負荷低減・資源循環率向上に貢献していく。
企業と生活者が協力して効率的な資源循環に取り組み、再生品の人気が高まることで、バージン材を使った製品が減り、再生材の価格が高騰する。また製品が繰り返し再生されることにより耐久性が落ち、製品寿命が短くなっていく。結果として、回収頻度が多くなり環境負荷の増加につながってしまうジレンマも生まれる。
再生品の循環を通して企業と消費者の間で「製品は共有財」という意識が育まれるが、安全性などの観点から耐久性の落ちたモノを廃棄したい企業と、長く使い続けたい消費者との間で軋轢も見え始める。消費者の中にはコミュニティを形成して、企業側の一方的な判断で製品を廃棄させない「修理する権利」を主張する動きも見られていく。