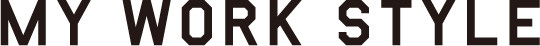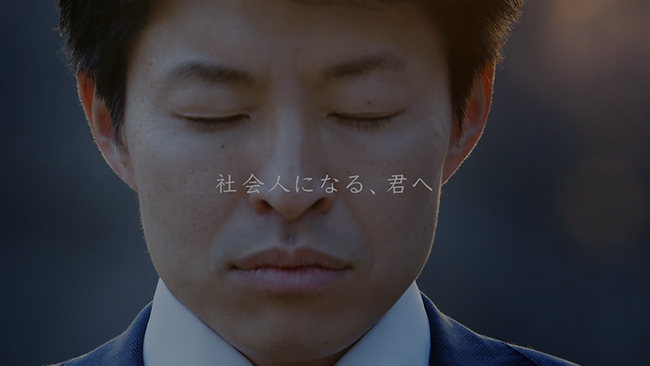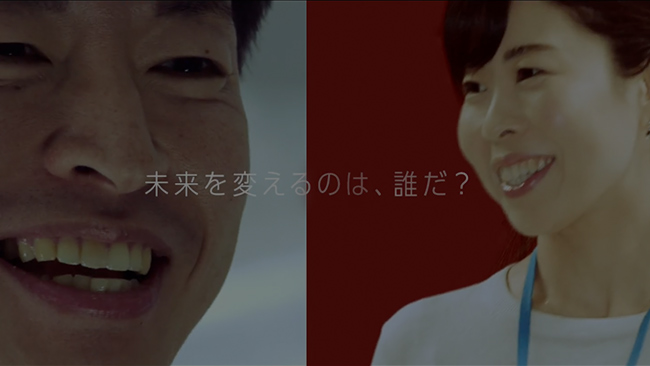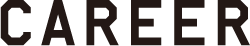
- 2019年
- 研究開発グループ サステナビリティ研究統括本部に配属。
- 2019年〜2024年
- 産業用電源システムに使用されるパワーデバイスの研究開発。
- 2024年〜
- 産業用電源システムの研究開発。
現在の仕事

カーボンニュートラル社会の 実現に向けて 産業のGXを推進する。
私たちの部署は、カーボンニュートラル社会の実現に向けて、産業のGX(グリーントランスフォーメーション)を推進するシステムと技術を開発しています。私が現在取り組んでいる研究テーマは「産業用電源システムの研究開発」です。10年先を見据え、冷却技術やエネルギーマネジメント技術の研究者を含む多部門連係のもと、研究開発を推進しています。例えば、近年のAIの急速な普及に伴い、データセンタの電力消費が増加しています。こうしたエルギー需要の高まりを受け、環境負荷の小さい電源システムの実現をめざし、再生可能エネルギーと連携した高効率な電力変換技術を開発しています。入社当初は、「産業用電源システムに使用されるパワーデバイスの研究開発」に取り組んでいました。パワーデバイスというのは、電源システムを構成する重要な半導体デバイスです。そこで得た知見や技術を活かして、現在の研究開発に取り組んでいます。
仕事のやりがい

多様な視点を取り入れて 思考が深まる。
カーボンニュートラルをビジネスの視点からも実現させるという挑戦しがいのある目標に向けて、多様な専門分野の研究者と連携しながら主体的に取り組めることに大きなやりがいを感じています。入社当初から継続して取り組んできたパワーデバイスの研究開発では、パワーデバイスの技術を持つ事業部と電源システムの知見を持つ研究開発グループが連携し、市場・技術動向の調査から、コンセプト設計、試作品の開発まで私たちが主体的に推進しました。専門分野や担当業務が異なる仲間と連携する中では、知識の領域が異なるため、多様な意見が交わされます。自分がこれまで積み重ねてきたアプローチが指摘を受けることもありますが、それ以上に、新たな視点を得ることで思考が深まり、視野が広がる楽しさがあります。
今後のチャレンジ

新規事業を創出できる 研究者をめざす。
パワーデバイスの研究開発では、開発した試作品を顧客に提供することで、期待される性能や実用化に向けた要件について、貴重なフィードバックを得ることができました。この経験から、理論検討やシミュレーションの結果をもとに立てた仮説を、実際のユーザーとの対話を通じて検証しながら技術開発を進めることの重要性を改めて認識しました。技術だけに着目するのではなく、社内外のステークホルダーが将来直面する可能性のある課題について仮説を立て、それを検証するサイクルを迅速に回していくことが昨今の企業研究者に求められているのだと思います。現在取り組んでいる研究テーマでは、産業のGXを加速する新規事業の創出をめざしています。市場・社会の変化を分析しながら、ユーザーとの対話を重ね、電源システムの技術開発に取り組んでいます。
ある1日のスケジュール
| 06:30 | 起床 |
|---|---|
| 06:30-08:00 | 朝食、子どもを保育園へ送る |
| 08:00-09:00 | 通勤 |
| 09:00-12:15 | 解析業務 |
| 12:15-13:00 | 昼食 |
| 13:00-14:00 | チーム内会議 |
| 14:00-17:00 | 実験 |
| 17:00-18:00 | 資料作成 |
| 18:00-19:00 | 退勤 |
| 19:00-24:00 | 夕食、家族団らん、読書 |
| 24:00 | 就寝 |
職場環境の特長
職位や年次に関係なく、お互いの専門知識やスキルを共有し合う、オープンな雰囲気の職場です。研修も充実しており、意欲があればさまざまなことが学べます。私は、5カ月間、イノベーションのプロセスを「体感」する研修に参加しました。4人一組で新規事業のアイデアを練っていくのですが、研修の最後にアイデアを発表した際に、多くの研修参加者から好意的な評価をいただき、新規事業をつくるという目標にもつながりました。

茨城は海や山が近くにあり、休日は家族と一緒に豊かな自然の中でリフレッシュしています。一人の時間があるときは、研究所のメンバーと集まってバンドの練習をしたり、読書をしたりしています。研究者は凝り性が多く、ギターのエフェクターを自作しているメンバーもいますよ。
学生時代・入社の決め手
-

学生時代
大学院では産業用電源システムに使用される磁性部品の損失解析を研究し、技術の向上には、システム全体を俯瞰して周辺分野を含めて課題を発見することが大切だと学びました。また、在学中にデンマークの大学に留学し、現地の学生と共同研究する機会を得ました。食事や雑談を通じて相手の背景や文化を理解しようと努めた結果、議論が活発になり研究が円滑に進むようになりました。彼らの勤勉さや研究レベルの高さに触れ、国際的な環境に身を置きたいと考えるようになりました。
-

入社の決め手
工学における俯瞰(ふかん)的な視点を養うため、他分野の専門家と連携しながら、技術開発から事業化・市場展開までのプロセスを実践したいと考え、総合電機メーカーの研究職を志望しました。日立は手がけるシステムのスケールが大きく、多様な基盤技術を持っていることから、幅広い技術領域に携われると考えました。また、国際的な環境で海外の研究者と切磋琢磨できる機会への期待もありました。
学生のみなさんへメッセージ

日立は社会イノベーション事業に取り組み、多様な分野の専門家と連携しながらプロジェクトを進めています。自身の専門性を発揮しながら、異分野の知識や視点を学べる機会も多く、新たな発見や洞察を得る機会も豊富にあると思います。研究者・技術者として成長しながら、社会課題の解決に直接貢献できる環境は大きな魅力だと思います。
MOVIE
- 「未来を変えるのは」編
- 「未来を変えるのは、私」編